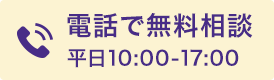本件は片側1車線の道路で起きた自転車と自動車の衝突事故です。事故により、被害者の男性にはびまん性軸索損傷による重い後遺障害が残ってしまいました。裁判の結果、被害者には1億5千万円以上の損害があると認定された事例です。
なお、本件は被害者の慰謝料を含む損害額を中心に紹介します。なるべく専門用語は避け、わかりやすく書いています。
目次
事故の発生状況
関東地方のある県で交通事故が発生した。片側1車線の道路を横断した自転車と直進してきた自動車が衝突した事故である。
当時、対向車線は渋滞しており、自動車の運転手は横断する自転車を確認することが難しかった。17歳の男性は渋滞中の車両の間を横断し、結果として自動車と衝突してしまった。頭を強く打った被害者はすぐに病院に運ばれ治療を受けた。病院による診断名は下記のとおりであった。
- びまん性軸索損傷
- 脳挫傷
- 左耳挫創
びまん性軸索損傷と診断された経緯
男性は約2カ月間にわたり一般の病院に入院。その後、別の一般病院とリハビリテーションセンターに入院し、入院期間は1年以上になった。退院後も約1年間、リハビリテーションセンターに通い、この時点で症状固定となった。症状固定時の診断書は下記のとおりである。
- 外傷性脳損傷
- びまん性軸索損傷
- 高次脳機能障害
- 体幹失調
自覚症状としては新しいことを覚える記銘力の低下や立位、歩行でのふらつきが見られた。他覚症状では高次脳機能障害に伴い、同時に注意を向け、情報を処理することが難しくなった。また、順序だてて作業を進めることにも支障をきたしている。また、話す時のリズムが不安定なので、電話で話が通じにくい。症状固定までの2年にわたって治療とリハビリテーションを行ったが、大きな改善は見られなかった。
その後も男性はリハビリテーションを続けた。症状固定から1年8カ月後、一般病院にて、びまん性軸索損傷による重篤な記憶障害や体のふるえなどの症状により、病院から一般就労を行うことは困難であり、就労能力はないと判断された。
びまん性軸索損傷による高次脳機能障害で3級に
症状固定後、後遺障害等級の申請を行ったところ、下記の等級に認定された。
| 別表第一 3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服するものができないもの |
|---|
びまん性軸索損傷の損害額をどう算定するかの争点
本件では事故による男性の損害と事故状況により、その損害をどのように算出するかが争点となった。争いは様々な分野に及んだが、主な争点は以下のとおりである。
1. 入院付添費
入院付添費は入院期間中に患者に付き添いをした者に対して支払われる。ただ、病院による「完全介護」の場合は病院側が患者の世話を一手に引き受けるという意味合いから、入院付添費は支払われないケースも多い。
加害者側は病院による「完全看護」から、日額3300円で124日を超える日数は損害を認めないと主張した。
本件では事故直後は重篤な意識障害であったことから、1日あたり6500円の入院付添費が認められている。
2. 退院後症状固定までの付添費用
男性はリハビリテーションセンター退院後から症状固定までの通院期間中も、日常生活全般において見守りが必要であった。そのため、入院付添費とは別に1日あたり5000円の付添費が認められている。
3.症状固定後の付添費用
被告側は付添介護の必要性を認めつつも、付添費用は1日あたり2000円を超えない金額と主張した。
被害者男性は日常生活動作は回復したものの、一部介助が欠かせない状態であることが確認された。また、記憶力や判断能力の低下から、見守りや声がけの必要性が認められた。付添費用は被害者男性が67歳になるまでは1日あたり4000円、67歳以降は1日あたり6000円が認められている。
4.逸失利益
逸失利益とは事故により得られなくなった将来の収入分である。後遺障害によって働けなくなった費用を補填するものとされる。しかし、被害者が若者の場合は費用をめぐって争われるケースが多い。
本件では被告が男性の労働能力喪失率が79%であることを主張した。男性は専門学校に進学する予定が確認され、男子労働者の高専短大卒の平均年収額程度の基礎年収が認められた。また、労働能力喪失率が100%であることも認められ、労働能力喪失期間も考慮されている。最終的に8300万円以上が認められた。
5.傷害慰謝料
けがをしたことに対する慰謝料の額は治療費と異なり、金額に関する特定の決まりはない。そのため、慰謝料の金額をめぐって争われる場合が多い。
本件は負傷の内容と治療経過などに照らし、400万円相当が認められた。
6.後遺障害慰謝料
自動車損害賠償保障法施行例(自賠法施行例)に定める等級の認定を受けたものを後遺障害という。後遺障害治療費は自賠法施行例に定める等級によって金額が決まる。
加害者側は後遺障害慰謝料の支払い額は1400万円を超えるものではないと主張した。しかし被害者の後遺障害が自賠法施行例別表第二の3級3号に相当することが確認され、1990万円の後遺障害治療費が認められた。
7.固有の慰謝料
障害によっては事故の被害者の内縁関係や婚約者など「近親者と同等」の方に固有の慰謝料が認められることがある。事故の被害者との関係性が同居等で生活を共にする時間が多く、経済的に扶養関係といった事実を立証すれば「近親者と同等」と認められる傾向にある。
加害者側は固有の慰謝料の支払いを認めなかったが、裁判では被害者の両親が受けた精神的負担が考慮され、固有の慰謝料として各100万円が認められた。
損害賠償額の合計
上記を合計すると以下の表のとおりとなる。
| 項目 | びまん性軸索損傷の賠償額 |
|---|---|
| 治療費 | 785万円 |
| 治療関係費 | 96万円 |
| 入院雑費 | 59万円 |
| 入院付添費 | 439万円 |
| 付添費 | 3303万円 |
| 交通費 | 13万円 |
| 逸失利益 | 8348万円 |
| 傷害慰謝料 | 400万円 |
| 後遺障害慰謝料 | 1990万円 |
| 合計 | 1億5435万円 |
弁護士に依頼するとどういうメリットが?
本件では、交通事故被害者のご家族が弁護士に解決を依頼しました。交通事故を弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか。
1 保険会社との交渉から解放される
治療中から長期間に渡って保険会社と交渉することにかかる負担は大変なものです。保険会社は少しでも支払額を抑えたいので、ご家族にかかるプレッシャーは相当なものがあります。弁護士が入ることで、難しい交渉をすべて弁護士が保険会社と行うため、長期間にわたるプレッシャーから解放されます。
2 将来への不安から解放される
保険金はすぐに支払われるわけではありません。最終的に支払われるまでに数年を要することもあります。どのようなプロセスで進んでいくのか、何を準備すべきなのか、心配が常に付きまといます。
弁護士は最終的な示談に向けてご家族をしっかりとサポート。支払われる保険金や慰謝料を最大化していきます。
3.弁護士費用を支払う以上の金額的メリット
交通事故でびまん性軸索損傷になると、介護が必要となりご家族の負担も大きいものになります。アズール法律事務所にご依頼される方の多くは仕事をやめ介護に専念しています。ご本人はもちろんのこと、ご家族の生活費も考慮する必要があります。
最終的な賠償額は保険会社に任せてしまうのと、弁護士に相談するのとでは億単位の差が出ることもありえます。弁護士費用を支払う以上のメリットをご家族にもたらすのです。
※本事例は、さいたま地方裁判所平成29年7月25日判決の事例をもとに構成されたものです。本事例は本事務所により提訴された事件とは異なっています。特定を避けるため、実際の事例とは若干異なった数値、記載をしています。あらかじめご了承ください。